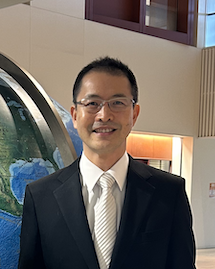| 氏名 | 古川 光明 |
| 職名 | 教授 |
| 専門分野 | 国際協力、開発経済論、地域研究(アフリカ) |
| 学位 | 博士(社会学) |
| 所属学会 | 国際開発学会 |
| k24007アットdokkyo.ac.jp (迷惑メール対策のため「@」を「アット」と表記しています) |
|
| 研究者情報(researchmap) | https://researchmap.jp/read0132374 |
研究紹介
私の現在の研究テーマは、南スーダンをケーススタディとして、紛争当事者である市民が外部支援や政府支援をどのように受け止めているのか、そのうえで、現地社会を巻き込む形で、どのように自らの慣習的統治機構や日常的な政治との関係で平和の実践を目指すのかを考察し、現地を重視した平和構築支援の枠組み構築に挑戦することです。最終的には、新しい平和構築論の流れのなかで現地主体の平和構築支援のあり方を政策提言として結実させ、これを国内外に発信できるような研究活動を行っています。
テーマ1:紛争影響下にある市民の外部支援・政府支援の受止め方に関する研究
概要:現地社会の視点に立って、和平合意プロセスやその実施において、周縁化された市民が外部支援や政府支援をどのように受け止めているのかを慎重かつ繊細に解きほぐすための、調査・分析を続けています。
キーワード:和平合意、政府支援、国際開発援助、市民、紛争
テーマ2:紛争の根源的な要因に関する研究
概要:同じ民族内、他民族や政府に対して生活を支える主要な生計資産との関係において、市民がどのような紛争認識を有しているのかを把握することで、現地社会に内在する紛争の根源的な要因を捉え直すことを試みています。
キーワード:紛争認識、主要生計資産、社会関係資本、政治エリート
テーマ3:紛争の根源的な要因に関する研究
概要:上記二つのテーマから分析される市民の政府とドナーの受け止めに関する認識と現地社会に内在する紛争の根源的な要因を探求するなかで、現在進行中の平和構築プロセスの適応状況を把握し、現地社会の主体性と慣習的統治機構や日常的な政治との関係を重視した平和の実践の方法を探っています。
キーワード:平和構築支援、状況適応型平和構築アプローチ、現地主体性、リベラル平和構築論、慣習的統治機構
担当授業科目名
国際開発論、国際公共政策論、専門英語、クラスセミナー(1年生),演習(2年生~4年生)
その他(活動,受賞,学会役員等)
2003年4月 – 2006年3月国際開発学会, 編集委員
2012年6月 – 2012年10月 文部科学省, 戦略的環境リーダー育成拠点形成評価作業部会委員
2015年:第19回「国際開発研究 大来賞」
2017年:「国際開発ジャーナル」創刊50周年記念 小論文コンテスト、審査員特別賞
2021年4月 – 2025年3月 独立行政法人国際協力機構中部センター, 草の根技術協力事業選考委員会委員
2018年11月 – 現在 国際開発学会, 編集委員
ゼミ紹介
ゼミ名
古川ゼミナール
ゼミのテーマ:国際協力(グローバル・サウスと国際開発援助)
グローバル・サウスへの国際開発援助の在り方を考える力を養うことを目的とします。
ゼミ概要
本演習は、グローバル・サウスへの国際開発援助の在り方を考える力を養うことを目的とします。卒業論文をまとめるためには、データ等により客観的に状況を把握した上で、論理的な考察を加える力が必要になります。ゼミでは、原則、テキストなどを用いて国際開発援助のニーズや課題の把握の仕方や問題意識の持ち方、解決策の考え方を学びます。具体的には、分担してテキストの概要を報告し、討議を行います。また、テキストの輪読後、各自が関心のある記事・論文等を選び、自らの考察を加えた形で報告し、討議を行うことで、卒業論文作成に向けた基礎的な力の養成を図ります。なお、国際協力で用いる参考文献は日本語に限らず、英語のものも活用します。自らが関心のあるテーマを選定していくなかで卒業論文のテーマを見出してほしいと思います。なお、「国際協力に関心があり、ゼミでしっかり勉強したい」学生さんを強く希望します。当然のことですが、ゼミの欠席や遅刻などは厳禁です。
推奨履修科目
国際開発論、国際公共政策論、開発経済学、国際協力学など
卒業論文のテーマ例
貧困や格差問題・紛争や暴力的過激主義・平和構築支援、難民支援・参加型開発、社会関係資本・教育問題・ジェンダー・保健医療・環境問題、自然災害・ガバナンス・開発援助の効果など
授業紹介
国際開発論a,b
「国際開発論」では、経済学部国際環境経済学科の学位授与方針(DP)及び教育課程の編成・実施方針(CP)が示す「持続可能な発展のための国際社会システムの構築を探り、国際的な相互依存関係において問題を捉える能力を身に付け」、「持続可能な社会の実現を目指して、地域社会や国際社会に貢献できる実践的な人材を育成する」ことに資するため、開発経済学のみならず開発社会学・開発政治学等を用いて経済発展に伴う開発課題を分析し、持続可能(Sustainable)ですべての人々にその恩恵が行き渡る(Inclusive)開発のための戦略・政策を検討します。そのことにより、開発途上国の経済・社会・制度上の問題と処方箋を包括的に理解します。
「国際開発論a」では、国際開発援助に関心のある学生を対象に、国際開発援助の変遷、国際開発援助における政策、オペレーション、開発援助の役割等を学習します。経済学のほか、政治学、社会学を用いて、開発途上国への国際開発を分析する基礎能力を習得すること目指します。「国際開発論b」では、経済発展の比較分析、貧困、人口動態・都市化、農業、教育・医療等の人的資本など、個別の開発分野について検討します。また、「開発経済学」等の課題や基礎理論を用いて、開発途上国の個別の開発問題を分析する応用能力を習得することを目指します。なお、担当教員の実務経験を踏まえた講義とします。
推薦教科書,図書
Michel P. Todaro and Stephen C. Smith, Economic Development 13th Edition, Addison Wesley, Pearson
関連科目
国際公共政策論、開発経済学、国際協力学など