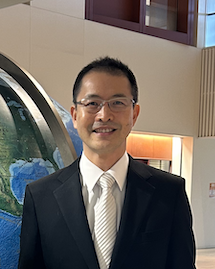| 氏名 | Mortha Aline (モルタ アリン) |
| 職名 | 専任講師 |
| 専門分野 | 環境経済学、エネルギー経済学、応用ミクロ計量経済学、気候変動政策、産業政策 |
| 学位 | 博士(経済学) |
| 所属学会 | 環境経済・政策学会 , Asian Association of Environmental and Resource Economics, International Association for Energy Economics |
| k25005アットdokkyo.ac.jp (迷惑メール対策のため「@」を「アット」と表記しています) |
|
| 研究者情報(researchmap) | https://researchmap.jp/alinemortha_00944498 |
研究紹介
応用ミクロ計量経済学手法を用いて、気候変動の効果を分析しています。
テーマ1:日本のカーボンプライシングと産業競争力 (2022年~現在)
炭素価格が導入されると、産業関係者の生産費用上昇につながることが多く、国際的な競争力低下への懸念を招く。
そのため、欧州連合(EU)は国境炭素調整メカニズム(CBAM)の導入を発表した。研究では、2014年の貿易データを用いて、CBAMが厚生、生産、輸出、排出量に与える影響をシミュレーションしている。その結果、CBAMは厚生にはほとんど影響を与えないものの、輸出の減少に寄与することがわかり、-0.29%(金属製品)から-1.49%(鉄鋼製品)の間で推定された。一方、輸出減少の影響で、運送活動による排出も減少する見込みがある。CBAMによる削減量は、この政策が2014年に導入されていた場合、およそ770百万トンCO2になると推定される。日本は2026年にEU排出量取引制度に類似した国内排出量取引制度(ETS)を導入する。産業競争力への潜在的影響を把握するため、2011年に埼玉県で導入された類似政策の事例を分析し、雇用、賃金、生産量、輸出への影響に焦点を当てる。
協力機関:経済産業省 (METI)、環境省 (MoE)
キーワード:国境炭素調整 (CBAM)、排出取引制度(ETS)、エネルギー集約的な部門の競争力
テーマ2:固定価格買取制度の再エネ賦課金の産業部門への影響 (2020年~2025年)
本研究の目的は 再生可能エネルギー普及のための賦課金導入による電力価格上昇がもたらすエネルギー集約的製造業への影響を把握することである。排出量変化の要因を、燃料・電力代替、燃料切替、エネルギー効率に分解し、電力を燃料に置き換えることが可能かどうかを検証する。まず、電力価格が1%上昇すると、自家発電用の燃料となる化石燃料の消費量は7%増加することがわかった。電力と燃料は代替材であるため、製造部門に対する(賦課金の)電力価格上昇の効果は、燃料消費量の増加、ひいてはCO2排出量の増加につながる可能性がある。賦課金の影響を推計した結果、自家発電や燃料切替により、工場内の排出量が13%(紙・パルプ)から52%(鉄鋼)増加させることがわかった。
協力機関:経済産業省 (METI)、環境省 (MoE)
キーワード:固定価格買取制度の再エネ賦課金、自家発電、電気と化石燃料の代替効果
テーマ3: 国際エネルギー政策の効果分析 (2019年~2024年)
本テーマは、二つの地域の分析におけるエネルギー政策の分析を行った。
まず、アジア発展途上国における様々なエネルギー政策の効果を分析した。例えば、各アジア諸国のエネルギー安全保障レベルを評価し、様々な政策選択肢を比較した。また、世界の他の地域と比較したアジアのグリーンボンドの特異性についても検証した。
次に、高所得世帯における省エネルギー行動および低炭素技術(太陽光発電など)の導入決定の背後にある決定要因を分析した。本研究の結果は、低炭素技術の導入に関する決定(特に導入費用が高い技術や構造上の要件を伴う技術)は、省エネルギーに関する決定に比べて、行動要因の影響を受けにくいことが示唆される。代わりに、教育水準と所得が、こうした決定をより大きな役割を果たしている。
協力機関:経済協力開発機構 (OECD)、アジア開発銀行研究所(ADBI)
キーワード:グリーンファイナンス、エネルギー安全、家庭調査、省エネ行動、低炭素技術の投資
担当授業科目名
経済政策a,b; Introductory Lectures; 経済学(マクロ); 経済学(ミクロ); 統計学入門; 経済経営数学入門; 演習 (2年~4年)
授業概要 (専門科目:経済政策論ab)
この講義では、経済問題を解決するための手段や方向性を示す経済政策を、理論的に解説することを通じて、各受講生が現実の経済の動きに対する洞察力を養うことを目的とします。すなわち、経済にかかわる新聞記事やニュースの背景等を学生自ら理解し、その方向性や解決策を理論にもとづいて提示できることを到達目標とします。本授業は二つに分けられ、経済政策論aにはミクロ経済学のアプローチをとり、経済政策論bはマクロ経済学のアップローチをとります。経済政策は狭義には政府の市場に対する介入と考えられており、その意味で政府が経済活動においてどのような役割を果たすのかが講義の中心的なテーマになります。具体的には、経済成長、完全雇用、物価の安定、資源配分の効率化、価格機構の整備、所得分配の公平化を図るために、経済政策(財政政策、金融政策、資源配分政策、産業政策・貿易政策、所得再分配政策)がどのように用いられるかを検討します。
その他(活動,受賞,学会役員等)
環境経済・政策学会 奨励賞 (2025年9月)
AAERE 2023年次学会 現地実行委員 (2023年8月)
早稲田大学高等研究所15周年記念シンポジウム パネリスト (2022年12月)
経済協力開発機構 外部コンサルタント (2022年10月~2024年8月)
ゼミ紹介
ゼミ名
グローバルエネルギー政策
ゼミ概要
近年、私たちはエネルギーとの関係や、持続可能な未来を確保するためのクリーンエネルギーの入手方法について再考する必要に迫られています。2000年代初頭から、気候変動に対する懸念が高まり、脱炭素化が世論の議論の中心になりました。さらに最近では、2022年のロシア軍によるウクライナ侵攻と経済制裁の必要性から、多くの国がロシアの石油とガスへの依存を見直す必要がありました。特に、天然資源に乏しい日本は、エネルギーの輸入に頼っている以上、国際エネルギー危機に脆弱性が高いです。そのため、日本のエネルギー政策を分析するためには、世界のエネルギー市場の変化を理解する必要があります。
本ゼミナールでは、世界のエネルギー政策、エネルギー市場とエネルギー価格、エネルギー安全保障、持続可能性と開発について、経済学的アプローチを用いて分析します。エネルギー市場は相互に絡み合い、エネルギー資源は地理的に集中しているため、エネルギー問題はグローバルな問題です。そのため、このゼミナールではグローバルなアプローチで問題に取り組みます。学生は初年次に英語の文献を読み、授業では国際的なケーススタディについて議論する予定です。