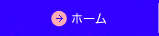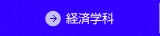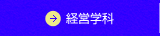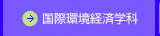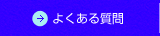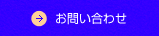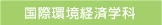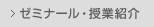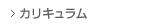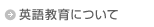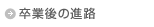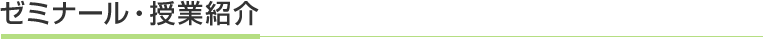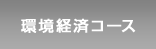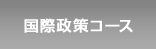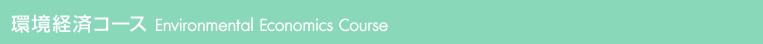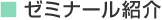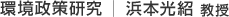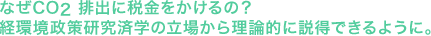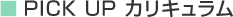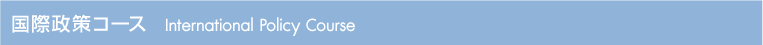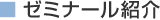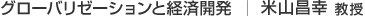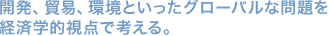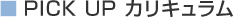社会科学のみならず自然科学まで含めた広い視野で環境を認識し、経済社会システムにおける人間の経済活動との関係において環境を正しく認識する能力を養います。環境と経済活動が両立できる社会の仕組みづくりを提案できる人材を育成します。
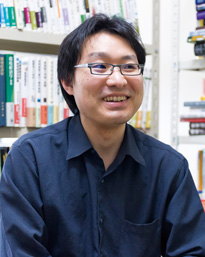
環境問題というと、日々のニュースなどでも馴染みの言葉である一方で、では実際どう取り組んだらよいのか、何が必要なのか、自分なら何ができるかと考えると実は難しい問題です。
私のゼミでは、環境や経済の知識に限らず、幅広い教養を身につけることを重視しています。
というのも環境問題は、いろいろな知識や観点をもつことで初めて検討できる、そういう性質のものだからです。ともすれば感情的に議論しがちなテーマですが、「ほんとうに社会全体のためになるとは…」という冷静で論理的な思考ができるようになることを目指します。
わかりやすい事例でいうと「CO2排出になぜ炭素税をかけるのか」という問題。環境経済学を学ぶ学生は、環境サービスを利用するには対価を支払わなければならないことやそのための社会の仕組みづくりを理解、提案できるようになっていきます。
卒業後はいま企業が求めている社会的貢献のできる人材として活躍できるでしょう。
-
- 地球環境論
- 現在の地球環境は長い地球の歴史の上でできあがり、今後も変化しうるものです。その構造と変動のメカニズムを、観測を含めて学びます。
-
- 地域生態論
- 現在の地球環境は長い地球の歴史の上でできあがり、今後も変化しうるものです。その構造と変動のメカニズムを、観測を含めて学びます。
-
- 環境経済学
- 環境破壊が進行する要因に関して経済学の立場から検討を加え、環境政策のあり方について考察するために必要な知識や理論を学びます。
-
- 環境政策論
- 原子力にかかわる問題、温暖化対策など、代表的な環境問題を取り上げ、環境問題に共通する構造を分析していきます。
-
- 資源・エネルギー経済論
- 21世紀における国際社会の持続可能な発展のため、安全・安定的かつ効率的に供給可能な資源・エネルギーに着目し、経済的に考察します。
-
- 環境ビジネス論
- 国内のみならず、世界各地のさまざまな生物多様性への取り組みを紹介しながら、企業にとっての生物多様性のありようを考察します。
経済学周辺の社会科学領域の科目を広く学んで、国際社会の抱える問題を国際的な相互依存関係において捉える国際的視野を養います。持続可能な発展のための国際社会システムの構築を探り、国際社会に貢献する人材を育成します。

私たちは国際経済社会のなかで相互に依存しながら生きています。グローバリゼーションの進展によって、先進国に住む私たちは豊かな生活を享受できています。近年、中国をはじめとする東アジア地域では貧困人口は大きく減少していますが、いまなお経済発展のハシゴに足をかけることさえできない国々がたくさん存在しています。また、途上国の経済開発が地球環境に与える影響も深刻です。
私のゼミでは、国際経済社会における貧困削減と持続可能な開発について経済学的視点から考えています。グローバルな問題に取り組むといっても、政府や国際機関の政策を考えるだけでは十分ではありません。ビジネスの仕組みをつくることや、日常生活を見直していくことも必要となってきます。
私のゼミには学生組織でフェアトレードに取り組んだり、NPO団体を通じてフィリピンやマレーシアにスタディーツアーに出かけたりする学生もいます。同じような問題意識をもった意欲的な学生が集まってくれるのを期待しています。
-
- 国際公共政策論
- 解決困難な経済社会問題に対して、より良い状況を生み出すために、各国が協力して行うべき政策・枠組みの形成等について学びます。
-
- 国際貿易論
- 国際貿易や貿易政策の基礎理論、貿易実務について学び、現実の国際貿易のテーマを考察するために必要な思考方法を修得します。
-
- 開発経済学
- 貧困問題、東アジア諸国の開発戦略などを取り上げ、将来企業人として開発途上国/新興国で活躍するために必要な知識や分析視角を学びます。
-
- 国際開発論
- 開発途上国の経済発展に伴う開発課題を分析し、持続可能ですべての人々にその恩恵が行きわたる開発のための戦略・政策を検討します。
-
- 開発社会学
- 歴史的かつ動態的な視点から、グローバル化時代における「開発と文化」「内発的発展論」「豊かさとは何か」という普遍的な命題を考えます。
-
- 国際NPO論
- 国際的なNPOまたはNGOについて全体像を理解し、事例研究を参照しながら、その成果と直面する課題について考察します。